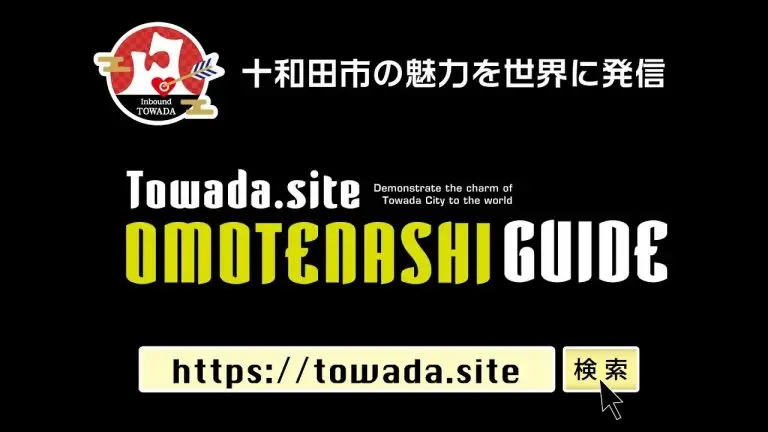和井内貞行
和井内貞行(わいない・さだゆき/1858年〈安政5年〉2月15日~1922年〈大正11年〉)は、盛岡藩鹿角郡毛馬内村柏崎(現在の秋田県鹿角市)に生まれました。和井内家は、毛馬内柏崎新城の城代を務めた桜庭家の筆頭家老を代々継いだ重臣の家柄で、父は和井内治郎右衛門貞明、母はエツ。幼名は「吉弥(きちや)」です。
武家の子として厳しく育てられた貞行は、明治維新の動乱における盛岡藩と秋田藩の戦争や敗北を幼くして経験しながら、郷里・毛馬内で成長します。
1866年(慶応2年)、9歳で盛岡藩の儒学者・泉沢恭助の塾に入門し学問を修めました。1874年(明治7年)、17歳で毛馬内学校(現在の鹿角市立十和田小学校)に教員手伝いとして奉職し、教育の道に携わります。
1878年(明治11年)、21歳で鎌田倉吉氏の長女・カツと結婚。1881年(明治14年)、24歳で工部省小坂鉱山寮に吏員として就職し、十和田湖畔にあった十輪田鉱山へ配属されました。当時の十和田鉱山は銀を産出し、最先端の精錬技術が導入されており、2,000人以上が生活する活気ある鉱山町でした。
厳しい自然に囲まれた十和田湖畔で暮らすなか、貞行は「魚の棲まない十和田湖に命を吹き込み、魚を棲まわせたい」という強い願いを抱くようになります。これが、のちに彼が命をかけて取り組むヒメマス養殖事業の出発点となったのです。

十和田湖
魚のいない十和田湖に挑む
かつての十和田湖には、魚が一匹も棲んでいませんでした。地元では「湖にまつられている青龍権現が魚を嫌っているため」と信じられ、魚が住まないのは神のたたりだと語り継がれていました。しかし、実際には十和田湖が外部の河川とほとんどつながっておらず、魚が自然に入り込めない閉ざされた地形だったことに加え、水温が低く栄養分も乏しいという、生物にとって過酷な環境が原因でした。
この迷信に対して、学問を修めていた和井内貞行は疑問を抱き、自ら湖を観察し、調査を重ねました。そして、27歳の時「十和田湖に魚を棲ませたい」という夢を抱き、養魚を決意。協力者を募り、何度も役所に足を運びました。「本当に魚が住めるのか」「神の伝説を破れるのか」といった不安や反対の声にも揺らぐことなく、信念を貫きました。
転機が訪れたのは、1884年(明治17年)のことでした。和井内貞行は、十和田鉱山長・飯岡政徳氏や宇樽部の開拓者・三浦泉八氏、後に鉱山長となる鈴木道貫氏とともに、鯉の稚魚600尾を十和田湖に放流しました。これは、鹿角郡長・小田島由義氏の許可を得た上で行われたもので、現在に伝わる中でも最も組織的かつ継続的な魚類放流の始まりとされています。和井内にとっても、これが本格的な養殖事業への記念すべき第一歩となりました。
なお、十和田湖での魚類放流記録としては彼が6人目、鯉に限れば3人目とされ、文献によれば、魚の放流は和井内によるものが初めてというわけではなく、1855年(安政2年)頃には、現在の十和田市沢田地区の角久平という人物が岩魚を放流したという話や、1879年(明治12年)には飯岡政徳氏が毛馬内方面から鯉1万匹を取り寄せて放流したとの記録も伝わっています。しかし、これらの試みは、広大な湖においては目立った成果を上げるには至らなかったようです。
翌1885年(明治18年)には、湖畔に新設された小学校の開校記念として、鹿角郡から寄贈された稚魚1,400尾が追加放流されました。和井内の放流活動は地域の教育や行政とも連携しながら進められていきます。
そして1889年(明治22年)、宇樽部付近の湖上で大きな鯉が跳ねる姿が目撃されるに至り、貞行の放流と養殖への情熱は一層高まっていきました。
この出来事が、後の「ヒメマス導入」という壮大な挑戦への布石となっていくのです。
1890年(明治23年)、和井内貞行は三浦泉八氏・鈴木道貫氏と連名で、青森県知事に対して十和田湖での養魚事業の申請を行いました。翌1891年(明治24年)にはその許可を正式に取得し、地域を巻き込んだ本格的な魚類養殖の第一歩が踏み出されます。
さらに1893年(明治26年)、同じ三浦・鈴木両氏とともに8年間にわたる湖水使用許可を取得。秋田県・青森県の両県からの正式な承認を得て、十和田湖における漁業権を確立することに成功しました。これにより、和井内の魚類放流・養殖活動は、民間主導の試みから行政公認の事業へと大きな転機を迎え、十和田湖を舞台にした養魚事業が本格的に動き出していきます。
この申請の時期には、湖岸において尺(約30cm)を超える鯉が泳ぐ姿が確認されたともいわれており、十和田湖でも魚が生きられるという確信が得られた重要な契機とされています。また、この願書とともに提出された副書の中には、すでに1885年(明治18年)に、子ノ口・銚子大滝に魚道を設ける計画を出願していたものの、当時は許可されなかったという記録も含まれており、これが和井内の活動に関する現存する最古の文書として知られています。
しかしその矢先の1894年(明治27年)、主な目的であった鉱山労働者への食料供給という養殖の意義が、十輪田鉱山の営業不振による休山によって失われてしまいます。さらに追い打ちをかけるように、小坂鉱山への転勤命令が下り、和井内の養魚活動は一時中断を余儀なくされました。
それでも和井内の志は揺らぐことなく、転勤後も十和田湖への思いを捨てることはありませんでした。そして1897年(明治30年)、40歳となった和井内は、当時日本有数の鉱山企業であった藤田伝三郎の「藤田組」を退職。ついに十和田湖へ戻り、ヒメマスの本格的な養殖に専念することを決意します。
和井内貞行の挑戦|ヒメマス養殖と観光地化への道のり
1897年(明治30年)、十和田湖に戻って養殖に専念する和井内は、鯉の出荷を始め、神戸で開かれた第2回水産博覧会にも鯉を出品しました。その後、東京や関西方面に出向いて繁殖技術や缶詰製造法を学ぶなど、養殖技術の向上にも努めました。
1899年(明治32年)、和井内貞行は長男・貞時とともに、事業の再起をかけて青森水産試験場から購入したサクラマスの卵を孵化させ、5,000尾を十和田湖へ放流しました。さらに翌年、日光養魚場から仕入れた日光マス(ビワマス)の卵を孵化させ、35,000尾を追加放流します。
こうして明治33年(1900年)には合計4万尾以上を放流するも、いずれの試みも結果は思わしくなく、期待された定着は確認されませんでした。事業は困難を極め、多額の借金を抱え、生活は困窮していきました。
そんな失意の中、貞行は青森市の東北漁業組合本部を訪問。その際に偶然出会った信州の寒天商人から、北海道・支笏湖に生息する回帰性のヒメマス「カバチェッポ(アイヌ語で“薄い小魚”の意)」の存在を聞かされます。この出会いこそが、和井内にとって「幻の魚」ヒメマスとの運命的な出会いとなり、十和田湖の新たな歴史が幕を開ける瞬間となったのです。
1901年(明治34年)、青森県水産試験場が阿寒湖原産・支笏湖育ちのヒメマスの卵20万粒を購入し、そのうち5万〜5万5千粒を和井内へ託しました。
1903年(明治36年)、ヒメマスのふ化に見事成功。およそ3万尾の稚魚を十和田湖に放流し、この新たな魚に「和井内鱒(わいないます)」という名を与えました。
そして1905年(明治38年)、和井内貞行は、日露戦争の勝利を記念して、秋田県鹿角郡小坂町十和田湖字生出(おいで)に、念願の十和田湖ふ化場を設置しました。
この施設は、ヒメマスの安定的な孵化・育成を目的としたもので、貞行にとっては長年の努力と苦難の末にたどり着いた、養殖事業の本格化を象徴する拠点となりました。
そして、この年、ついに放流されたヒメマスたちが群れをなして湖岸に帰ってきたのです。この感動の瞬間を目の当たりにした和井内は、「われ、幻の魚を見たり」と語ったと伝えられています。
さらに和井内は、養殖事業と並行して、十和田湖を観光地としても発展させようと尽力しました。1897年(明治30年)には旅館「觀湖楼(かんころう)」を開業し、1916年(大正5年)には本格的な宿泊施設「和井内十和田ホテル」をオープン。湖畔に訪れる人々を迎える体制を整え、観光と水産の両輪によって地域の未来を切り拓いていったのです。

道の駅十和田湖にある和井内貞行と妻カツの像
妻カツの支えと家族の献身
和井内貞行は、妻カツの支えなしには成功できなかったでしょう。お金がない中で9人の子どもを育てながら、ヒメマスの購入資金を工面するために、カツは愛用の着物や櫛、懐中時計を質に入れるなど、気丈に苦境に立ち向かいました。
1905年(明治38年)、ヒメマスが初めて帰ってきた年、東北地方は大凶作に見舞われました。多額の借金を抱えていた和井内家に対し、カツは「魚を地元の人々に自由に釣らせてあげよう」と夫を説得しました。その慈愛と強さから、カツは戦前の教科書で「良妻賢母」の模範として紹介されました。
和井内ホテルの裏庭には、かつて貧しさの中で使われた石ウスが残されています。カツはこの石ウスで豆を挽き、豆腐を作って行商に出かけ、家計を支えました。裕福な商家に育ったカツが、自らの手で生活を支える姿は、まさに献身の象徴でした。
1906年(明治39年)に発行された官報によれば、和井内貞行は1884年から1905年までの約20年間にわたって9,018円を養殖事業に費やし、漁獲による収入は2,650円にとどまりました。差額の6,300円は赤字で、現在の物価に換算すると3,000万円以上の赤字額ともいわれています。その苦難の中、長男・貞時は秋田中学校を中退せざるを得ませんでしたが、夫婦は諦めずに養殖の夢を追い続けました。

和井内神社
和井内神社と和井内夫妻の顕彰
1905年(明治38年)、ヒメマスの養殖を私財を投じて成功させた和井内貞行と、その妻カツの徳を慕い、十和田湖西岸の遊歩道沿いに「勝漁神社(勝漁社)」が建立されました。この神社は1908年(明治41年)、湖畔の住民たちの手によって創建されたものです。
翌1907年(明治40年)、和井内の功績が国に認められ、「緑綬褒章」が授与されました。しかしその直後、長年にわたって和井内を支え続けてきた妻・カツが病に倒れ、46歳の若さでこの世を去ります。湖畔の人々はその献身に深く感謝し、神社はカツの徳も祀る場所として親しまれるようになりました。
1922年(大正11年)5月16日、和井内貞行もその波乱に満ちた生涯を閉じます。享年65。その後、彼の霊は「勝漁神社」に合祀され、1933年(昭和8年)には社名が「和井内神社」へと改められました。
現在の拝殿は1977年(昭和52年)に改築されたものであり、かつては5月3日にカツの命日を偲ぶ春の祭礼、9月21日には和井内貞行の命日にあたる秋の例祭が執り行われていました。神社は今なお、十和田湖に命をもたらした夫婦の志を伝える静かな祈りの場として、多くの人々に敬われています。

道の駅十和田湖の隣にある”ふ化場”
養殖事業の継承と現在
1950年(昭和25年)の漁業制度改革を受け、翌1951年(昭和26年)には「十和田湖増殖漁業協同組合」が漁業権を取得。これを機に、ヒメマスの増殖事業が本格的に制度化され、1952年(昭和27年)には和井内貞行がかつて使用していたふ化施設を国が借り受け、「水産庁十和田湖ふ化場」が発足しました。
その後、1960年(昭和35年)には同ふ化場の管理が秋田・青森両県に移管され、両県による「十和田湖ふ化場協議会」が設立されました。翌1961年(昭和36年)には、国の助成を受けた上で施設を買い取り、新たな整備が実施されました。
1982年(昭和57年)には、ふ化場の管理・運営が十和田湖増殖漁業協同組合に委託され、さらに1986年(昭和61年)には同協議会が廃止され、ふ化事業そのものが漁協に正式に移管。施設も併せて譲渡され、地域主導による持続的な管理体制が確立されました。
そして2002年(平成14年)には、同組合によって最新の技術を備えた「十和田湖新ふ化場」が建設され、12月6日に竣工式が執り行われました。これにより、十和田湖ひめますの増殖体制はさらに強化され、安定供給への道が大きく開かれることとなったのです。
一方で、和井内貞行が明治期に築いた旧ふ化場跡は、現在では秋田県小坂町の史跡として保存され、その先駆的な挑戦と功績は今なお語り継がれています。和井内は「ヒメマス養殖の父」として知られるのみならず、旅館の開業や観光資源の開拓を通して十和田湖を観光地へと発展させた立役者として、「十和田湖開発の父」とも称される存在です。養殖技術に賭けた情熱と、地域の未来を見据えた取り組みは、今も多くの人々の記憶とまちづくりの礎に息づいています。

十和田湖ひめます


商標登録と「十和田湖ひめます」ブランド
それまで、アイヌ語で「薄い小魚」を意味する「カバチェッポ」と呼ばれていたヒメマスは、1908年(明治41年)、北海道水産試験場の森脈技師の提案により、その小ぶりで美しい姿から「紅の小なるは姫に通ず」と評され、和名として「姫鱒(ヒメマス)」の名が正式に命名されました。
「姫鱒(ヒメマス)」はサケ科に属する淡水魚で、紅鮭の陸封型──本来は海に下る習性を持ちながら、湖の環境に適応し一生を淡水で過ごすようになった種です。「十和田湖名物の姫鱒(カバチェッポ)」として親しまれ、その美しい姿と味わいから、十和田湖の自然と食文化を象徴する存在へと育まれてきました。
そして、2015年(平成27年)には、「十和田湖ひめます」として地域団体商標に正式登録され、ブランド化が本格的に進展。同年、十和田湖増殖漁業協同組合は十和田市の補助を受けて急速冷凍設備を導入。電解水による殺菌、真空包装、マイナス40度での急速冷凍、冷凍保存までを一貫して行える体制が整備され、解凍後でも刺身として提供できる品質が保たれるようになり、料理人からは「生魚と遜色ない」と高い評価を受けるようになりました。
さらに、十和田市と小坂町が事務局を担う「十和田湖ひめますブランド推進協議会」では、認証制度の導入、メニュー開発、食イベントなどを通じてブランド価値の向上に取り組んでおり、「十和田湖ひめます」は、地域の特産品として注目を集めています。
十和田湖ひめますの大きな魅力は、美しい紅色の身と繊細な味わいに加え、アスタキサンチンやアンセリンといった健康成分を豊富に含んでいる点にもあります。刺身では脂の乗った柔らかな食感と上品な甘みが際立ち、塩焼き、天ぷら、カルパッチョ、コロッケ、姿寿司など、地元の飲食店でもさまざまな形で提供され、十和田湖を訪れる人々の舌を楽しませています。

十和田湖を眺める位置にある「道の駅十和田湖」
和井内貞行とカツ夫人の銅像建立と道の駅十和田湖
2024年(令和6年)10月12日、十和田湖畔に新たに誕生した「道の駅十和田湖 ひめますの郷・和井内」(秋田県小坂町)に、「ヒメマス養殖の父」「十和田湖開発の父」として知られる和井内貞行と、その妻カツの銅像が建立されました。
この道の駅は、八幡平と十和田湖を結ぶ観光の拠点として整備され、秋田県側から十和田湖を訪れる際の玄関口としての役割も果たしています。施設内には、レストランやお土産コーナーのほか、「十和田湖ひめますの郷展示室」が併設されており、十和田湖の成り立ちやヒメマス養殖の歴史、和井内貞行の功績を紹介するパネル展示や「ヒメマスシアター」などが楽しめます。
道の駅の中心に据えられた和井内夫妻の銅像は、その偉業を訪れる人々に語りかけるように佇み、彼らの歩んだ歴史と地域への貢献を今に伝えています。
🔗 関連記事|十和田湖ひめますをもっと深く知るために
🐟 十和田湖の魚たち12種を解説
ヒメマス・ワカサギなど、代表魚を写真つきで紹介。自然観察にもおすすめ!👤 幻の魚を蘇らせた 和井内貞行
「われ、幻の魚を見たり」──命を宿した男の挑戦と功績。🍽️ ひめますの魅力とおすすめの食べ方
ブランド化の歴史から味の特徴・絶品料理までを徹底紹介!🌄 神秘の湖・十和田湖の絶景と歴史
四季の景観、神話、観光スポットを網羅した保存版ガイド。